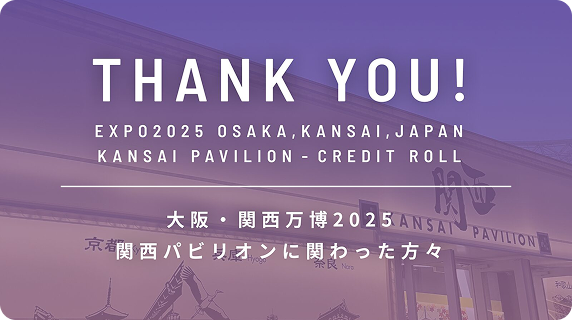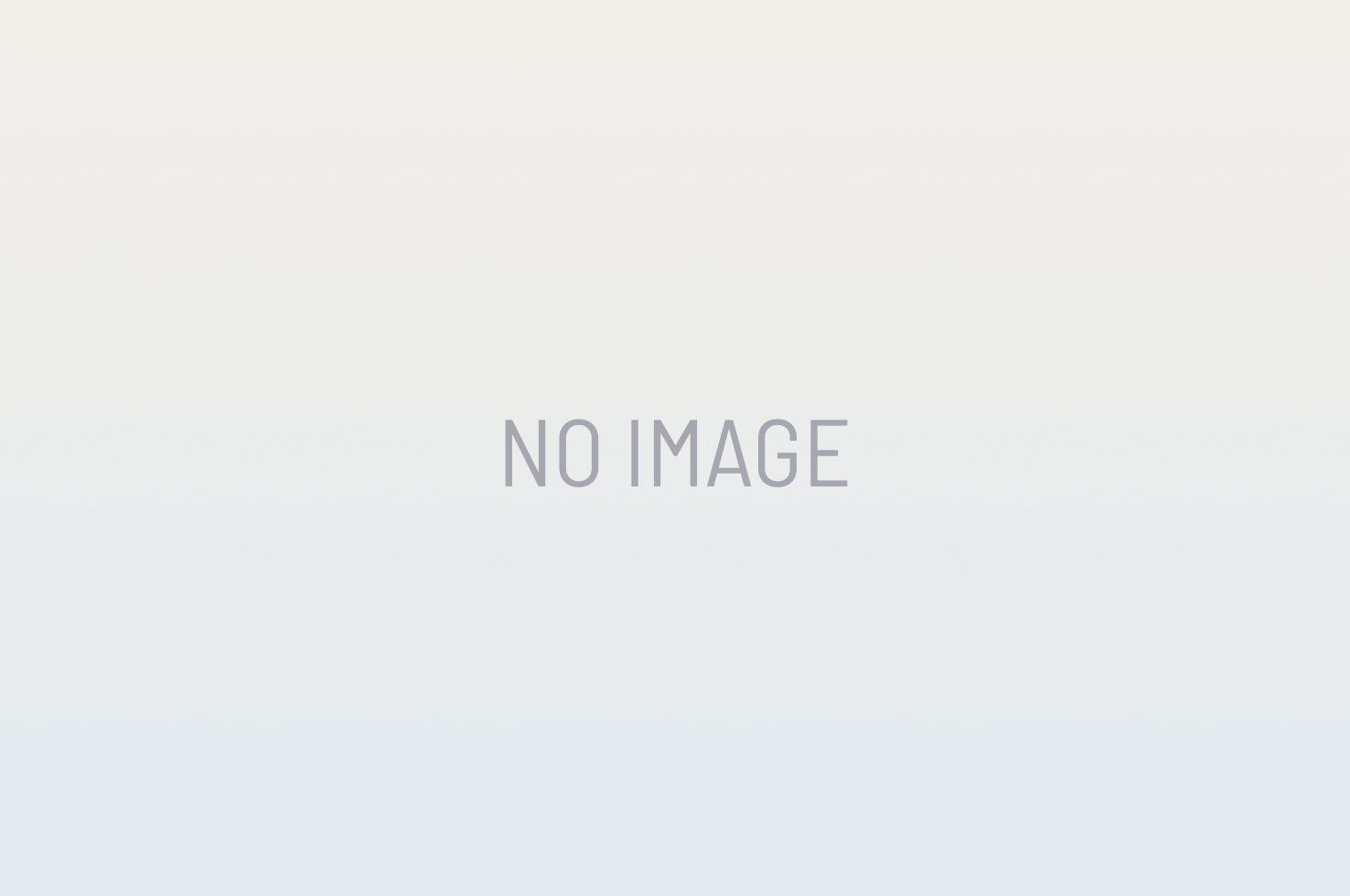クフ王ピラミッド、始皇帝陵と並ぶ世界3大墳墓、5世紀中ごろ築造とされ全長約486mの日本最大の前方後円墳。百舌鳥耳原三陵の一つで、墳丘は3段に築成され三重の濠がめぐり10基以上の陪塚があります。
エジプトのクフ王のピラミッド、中国の秦の始皇帝陵と並ぶ世界3大墳墓の一つといわれ、上空から見ると円と四角を合体させた前方後円墳という日本独自の形で、5世紀中ごろに約20年をかけて築造されたと推定されています。日本最大の前方後円墳で北側の反正天皇陵古墳(田出井山古墳)、南側の履中天皇陵古墳(ミサンザイ古墳)とともに百舌鳥耳原三陵と呼ばれ、現在はその中陵・仁徳天皇陵として宮内庁が管理しています。前方部を南に向けた墳丘は全長約486m、後円部径約249m、高さ約35.8m、前方部幅約307m、高さ約33.9mの規模で3段に築成されています。左右のくびれ部に造出しがあり、三重の濠がめぐっていますが、現在の外濠は明治時代に掘り直されたものです。葺石と埴輪があり埴輪には人物(女子頭部)や水鳥、馬、鹿、家などが出土しています。
昭和30年代と最近の調査で造出しから須恵器の甕が出土し、古墳が造られた年代を知る資料として話題になっています。明治5年(1872年)には、前方部で竪穴式石室に収めた長持形石棺が露出し、刀剣・甲冑・ガラス製の壺と皿が出土しました。出土品は再び埋め戻されたといわれていますが、詳細な絵図の記録があり、甲冑は金銅製の立派なものだったようです。
日本最大の前方後円墳にふさわしく、周囲に陪塚と考えられる古墳が10基以上あります。仁徳天皇陵とされていますが、日本書紀などに伝えられる仁徳・履中の在位順とは逆に、履中天皇陵古墳よりも後で築造されたことがわかっています。