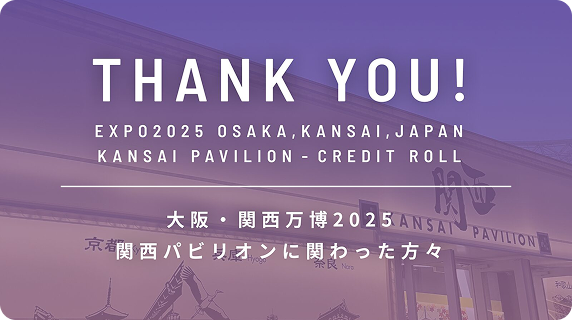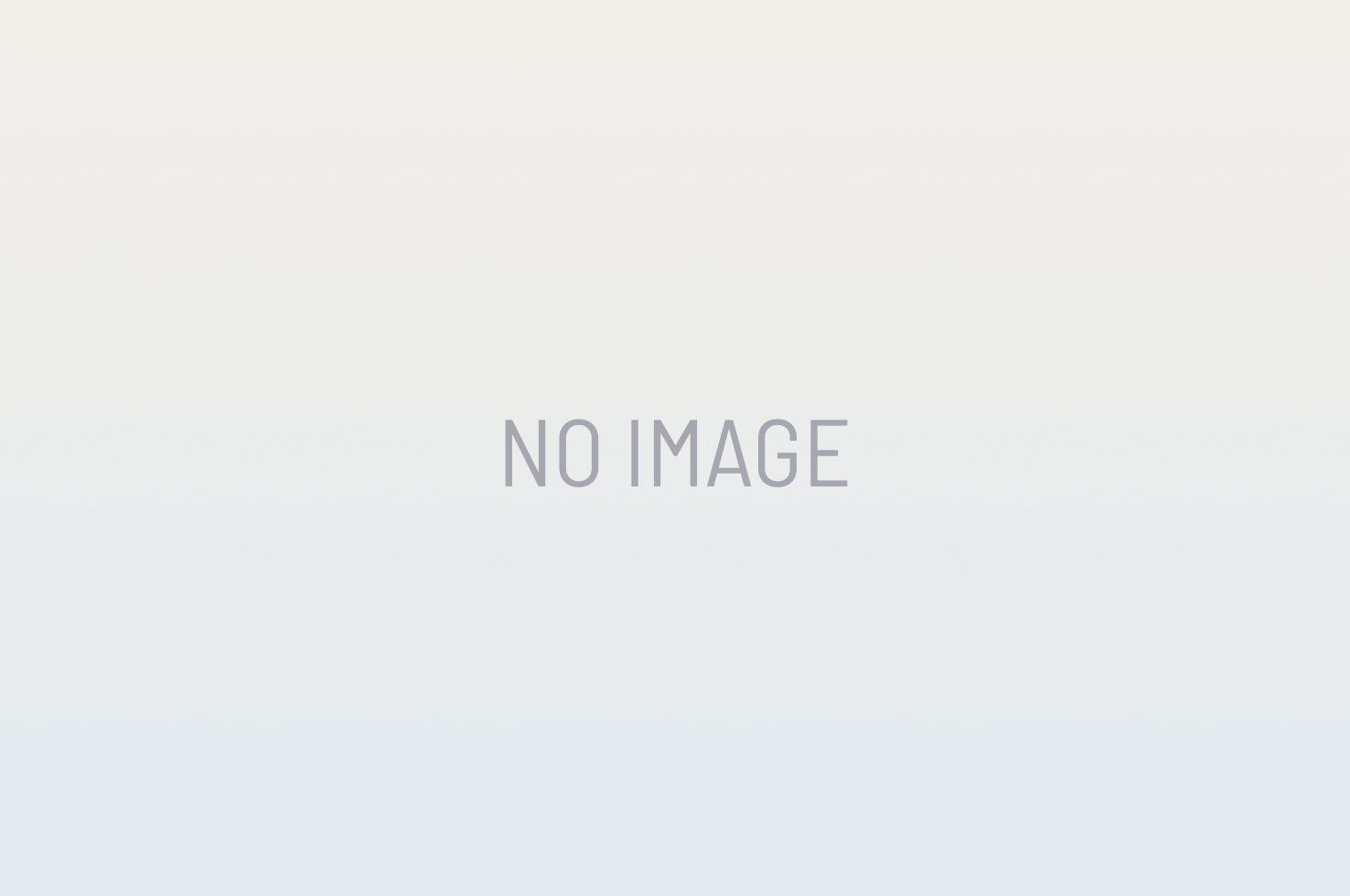境内は一面に緑の美しい苔で覆われ「苔宮」「苔寺」とも呼ばれますが、現在は明治の神仏分離令により寺号を廃止し、白山神社となっています。
養老元年(717年)に泰澄大師によって開かれたと伝わり、白山信仰の越前側の拠点となりました。平安後期には天台宗比叡山延暦寺の末寺として発展し、最盛期の戦国時代には、48社、36堂、6,000の坊院が建ち並び、寺領は9万石・9万貫、8,000人もの僧兵がいたと伝えられ、当時は日本屈指の宗教勢力であったようです。
天正2年(1574年)、織田信長方に属していた白山平泉寺は、越前の一向一揆勢に攻められ全山が焼失、10年後に一部再興されましたが、境内は元の10分の1程度にすぎず、多くの坊院跡は山林や田畑の下に埋もれました。
白山平泉寺の境内は、現在の平泉寺区集落を含む東西約1.2km、南北約1.0kmの範囲と推定され、平成元年(1989年)から始まった発掘調査によって、当時の遺構がそのまま平泉寺区の地中に埋もれていることが判明。遺跡の広大さや保存状態が良好であることから、旧境内全域が国史跡に拡大指定され、名称も「白山平泉寺旧境内」となりました
泰澄を白山に導いた女神が現れたと伝わる御手洗池や、全山焼失に耐えて残ったと伝わる大杉など往時の白山平泉寺の姿をしのぶことができ、中世の遺跡としては国内最大級の見事な石敷道や、斜面を階段状に整えながら続く坊院群の跡を見ることができます。すぐ近くの総合ガイダンス施設「白山平泉寺歴史探遊館まほろば」では、白山の歴史や自然を学ぶことができます。
「平家物語」では木曾義仲の「火打合戦」に登場し、「義経記」にも源義経が「有名な平泉寺に行きたい」と立ち寄った話が描かれています。
明智光秀の人生を描いた「明智軍記」では朝倉家滅亡を描いた記述に多数登場します。