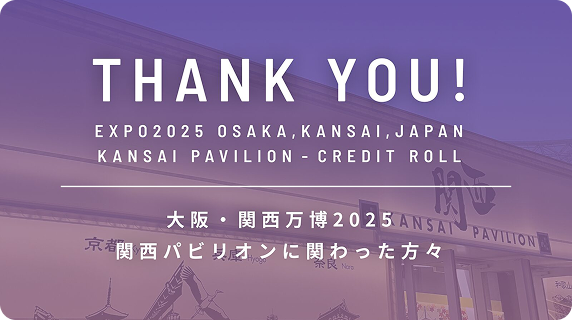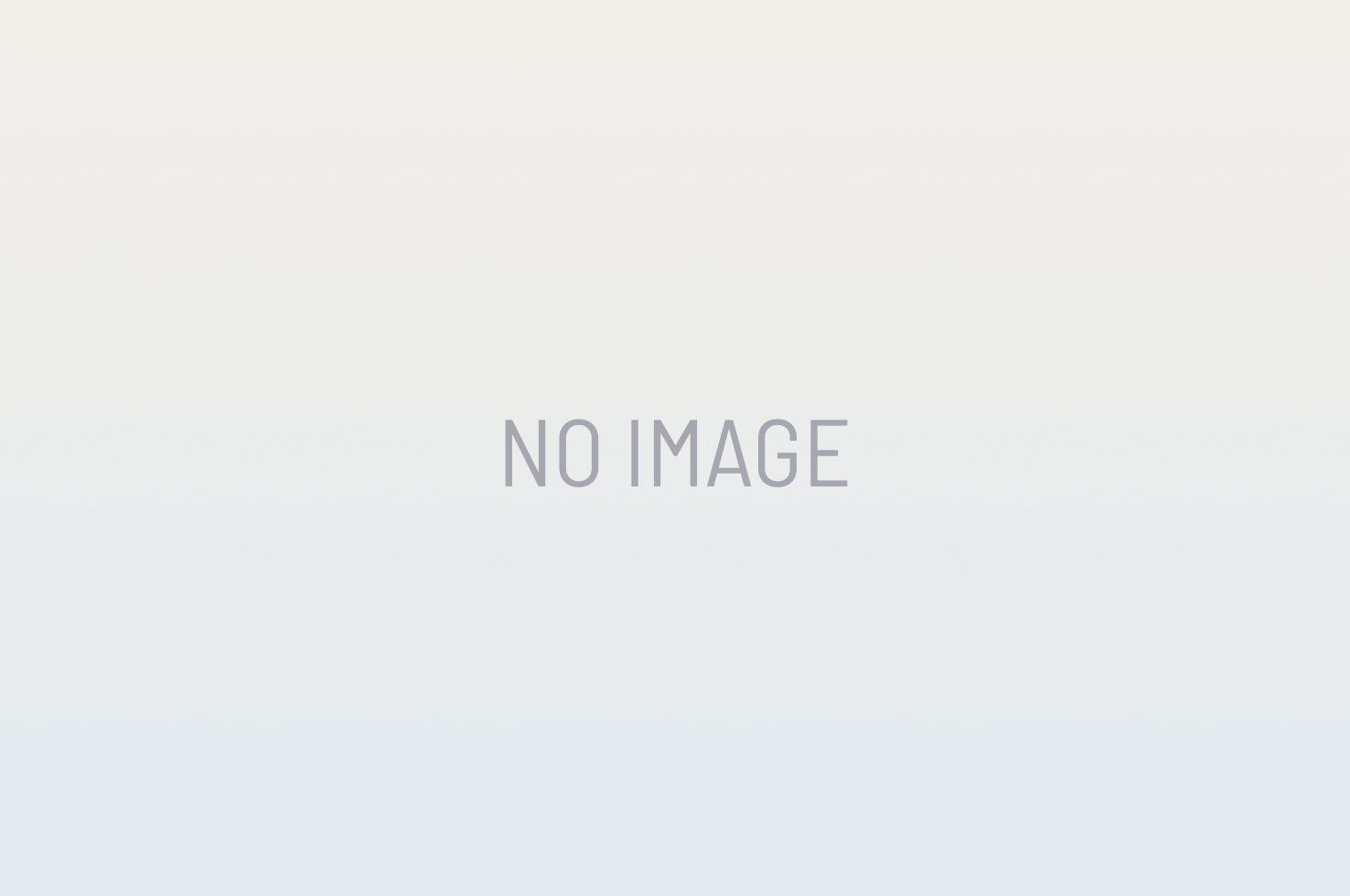松花堂庭園には、絵のように美しい景観、伝統的な茶室と茶道(茶の湯)に関連するその他の歴史的な建物、そして美術館があります。40種以上の竹、約300本の椿、モミジ、そしてその他の多くの植物が、22,000平方メートルの敷地内に茂っているおかげで、この広々とした庭園には一年中楽しめる季節のものがあります。
この庭園の名前は松花堂昭乗(1584~1639)という、近くの男山にあった石清水八幡宮寺の寺院の一つに住んでいた僧侶に由来しています。彼は優れた茶師、そして芸術家として有名であり、当時の三大書家の一人とみなされていました。内園には、昭乗の草庵と、彼の隠居寺の客殿があり、内園は国の名勝となっています。
八幡市は、草庵と寺院の客殿の所有権を取得し、これらの建物を保存するため、そして八幡の文化的な遺産の顕彰を目的として、1977年に松花堂庭園を設立しました。茶室建築の進化のさまざまな段階を表す3つの伝統的な茶室の復元が外園に追加され、茶会や文化イベントの開催にも定期的に利用されています。
松花堂美術館の常設展では、松花堂昭乗の生涯と作品に焦点を当てています。その他にも、男山と八幡の歴史・文化に関する作品を展示するさまざまな展覧会を、年間を通して開催しています。